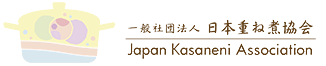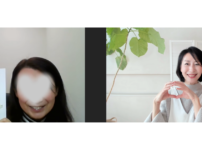花粉症の改善法、風邪の手当てを
ご紹介してきましたが、
子供の風邪~熱がある時~手当てシリーズ⓺~
子供の風邪~熱がある時~手当てシリーズ⓻~
子供の風邪~熱がある時~手当てシリーズ⓼
子供の風邪~熱がある時~手当てシリーズ⓽
頭に置いていただきたいのは
「手当ては対症療法」ということ。
日常的、長期にわたって使うものではありません。
かくいう私も15年ほど前は、バイブル書をくまなく読んで、
息子を実験台のように
可能な限りの手当てを施していました。
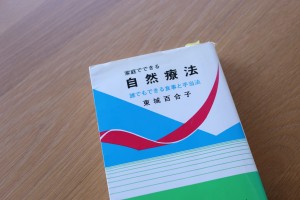
15年前、3歳だった息子は
アトピー性皮膚炎、気管支喘息のアレルギー症状に加え
身体がとにかく弱い。
1歳の時にかかったインフルエンザは重症化し、救急病院と点滴のお世話になり、
ノロウィルスももちろん重症化。
1か月に1度は熱を出し、熱が出ると3日は下がらない、
蓄膿症もひどくなったことがありました。
予防注射をすれば副反応を起こして発疹、発熱。
(→これがきっかけで予防注射について調べるようになり、
接種をやめました。)
まさに病気のデパート。
「病院通いだった自分を変えるぞ!」と意気込んでいたので、
熱が出ると、近所の公園へビワの葉を取りに行き、
お腹が痛いとこんにゃく湿布をしたり、
傍から見ると滑稽だったのではないかと思います。
その手当てで良くなったか…
なりませんでした!
手当て法を沢山知っていて、いつでも施せる
=家族の健康を守れる
ではないのです。
大切なのは手当て法より何よりも日々の家庭での食事。
「台所は家庭の薬箱」です。
今はそれが一番の養生であり、手当てだと
実感しています。
気をつけたい3点はこちら。
1.食事を整えること。
整えるとは、お米・味噌汁・野菜・魚(たまにはお肉)を食の中心にすること。
自然治癒力、免疫力がつき、 体調を崩しにくくなります。
2.食べ過ぎないこと。
腹8分目とはまさに。胃腸の疲れは不調のもと。
胃腸が疲れてくると免疫力もガクンと低下してしまいます。
3.会話をすること。
会話をすると体の調子、心の調子がわかります。
調子が悪い時は油ものをやめて消化のよいものを作るなど
早めに食事での対応も可能です。
私たちの周りにはあらゆる健康法があります。
私自身、
ホメオパシーに興味を持ったこともあり、
テルミー、アロマを勉強したこともあります。
ですが、全ては対症療法。
大切な根っこは家庭での日々の食事。
日々の生活。
ここを整えてこそ、
不調な時の手当て法もチカラをかしてくれるのです。
現在、高校生と小学生の二人の息子は
時々お腹が痛い、喉が痛いというのみで
最小の手当てをする程度。
大きな病気にかかることがなく、
病院へ行くことなくすんでいます。
毎年猛威をふるうと脅かされるインフルエンザの
予防注射は副反応が出て以来、受けていないですが、
長男は1歳の時にかかったきり
次男はまだかかっていません。
今年もどうやら乗り切れそうで安心していますが、
油断は禁物。食べ過ぎ注意報を徹底継続中です。